|
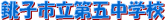 |
|
|
|
|
|
|
| 令和元年度 学校経営方針 |
| |
1 教育目標 (令和元年度)
|
|
(1) 学校教育目標
生きる力を身につけ 、主体的に行動できる生徒の育成
(2) めざす学校像
- 活力に満ち 、磨き合い 、互いに伸びる学校
- 安全で安心して学べる学校
- 健康で情操豊かなうるおいのある学校
- 信頼され地域とともにある学校
(3) めざす生徒像
生きる力 「確かな学力」 「豊かな心」 「健やかな体」
- 自ら進んで学習する生徒 確かな学力
- 思いやりがあり 、進んで奉仕できる生徒 豊かな心
- きまりや約束を守れる生徒 豊かな心
- 自ら鍛え 、たくましい精神力と体力を持った生徒 健やかな体
(4) めざす教師像
- 自らの使命を自覚し 、健康で明るく前向きに取り組む教師
- 生徒の気持ちを心で視て聴いて 、受容できる教師
- 生徒への指導や支援の力量を磨き 、共に伸びる教師
- 危機管理意識を持ち 、事故防止に努める教師
|
2 経営方針
|
- 学習指導要領、県、市の教育指導の指針に即し 、生徒や学校の実態を踏まえ 、明るい未来を切り拓くための「生きる力」の育成に努める。
- 確かな学力を身につけるため 、指導方法を工夫し、育成すべき資質・能力をバランスよく育む。
- 生徒一人一人の良さや可能性を見いだし個性を伸ばしながら 、豊かな人間性や社会性を育てる。
- 体育・健康教育を充実させ 、健康的な心身を育てる。
- 学校の教育活動全体を通じて、教師の意図的な指導・支援により、生徒の主体性を育てる。
- 目標申告シートの効果的な実施により 、教職員個々の力量を高め 、組織的・計画的に学校教育目標の具現化を図る。
- 特別支援教育の充実を図るため 、全教職員が理解の上、協力し合い学校全体としての対応を組織的
、計画的に進める。
- 家庭・地域・関係諸機関と連携し 、安全でうるおいある学習環境を保ち 、学校評価や学校公開の実施により
、信頼され地域とともにある学校づくりに努める。
- 学校評価の有効的な活用により 、常に改革・改善の視点に立った学校経営を行い
、PDCAサイクルによる教育活動の質的充実を図る。
- 教職員一人一人が、業務改善の意識を持ち、業務を見直し、効率化を図る。
|
3 経営の重点
|
(1)学習指導の充実
- 主体的・対話的で深い学びを通し、知識及び技能、思考力・判断力・表現力等、学びに向かう力・人間性等をバランスよく育む。
- 確かな学力を育むため 、必要な授業時数を確保するとともに 、学期毎の評価を基に、目標を持たせ、長期休業中の効果的な学習を促す。
- 本校で作成した「家庭学習の進め方」を基に、家庭学習の充実を図る。
- 学習規律を徹底し、生徒一人一人の興味・関心・能力等を引き出し、学習意欲の向上や学習習慣づくりを働きかける。
- 授業改善を積極的に進め 、思考力・判断力・表現力などの育成に努める。
- 授業のねらいに即した一人一人の指導を工夫し 、指導目標の達成を図る。
- 少人数指導(数学・英語・理科)の実施により 、個に応じた指導の推進を図る。
- 質問しやすい雰囲気を整えた授業展開に努める。
(2)思いやりのある豊かな心・健やかな体づくりの充実
- 道徳教育・ふるさと学習・福祉教育を積極的に実践する。
- 道徳の時間の授業時数を確保し、一層の充実を図る。
- 学級担任・学校栄養職員(栄養教諭)・養護教諭との連携により食育の推進を図る。
- 防災教育を進め 、危険を予測・回避する的確な行動のできる能力を育てる。
(3)生徒指導の充実
- 職員朝礼や生徒指導部会・学年主任会・学年部会・職員会議等を通して 、生徒についての情報や指導方法を共有し 、共通理解を図る。
- 生徒指導に関する共通実践事項を毎週1〜2項目設定し 、全校を挙げて生徒指導上の課題解決を図る。
- 生徒指導部会を毎週開催し 、生徒指導主事を中心に学年・養護教諭・スクールカウンセラー等との連携を強化し
、機能的な校内指導体制の確立と 、組織的 、計画的な生徒指導の推進に努める。
- 生徒一人一人に対する理解を深め 、個に応じた指導・支援に努める。
- 体験的活動を通して 、自主的で協力的な態度を養い 、豊かな心と実践力の育成に努める。
- 家庭や関係機関等と密接な連携を図り 、適応指導・いじめ・不登校等に関する指導の充実に努める。
- いじめはあるという視点に立ち 、すべての教育活動において、いじめの予防・早期発見・早期解決を図る。
- 携帯電話等アンケート調査による実態把握と情報モラルの向上に努める。
(4)キャリア教育の充実
- 学級指導や総合的な学習の時間を中心とした進路学習及び様々な体験を通し 、将来に対する明確な目的意識を確立できるようにする。
- 様々な体験活動を実施し 、他との関わりにおいて達成感や自己肯定感、基礎的・汎用的能力を育て
、それを基盤として 、希望と自信を持って積極的・意欲的に自己の進路を考える姿勢を育てる。
- 諸調査等により適切な情報を収集し、進路相談等により 、生徒一人一人の能力
、適性及び進路希望などを十分把握し 、生徒自ら適切な進路選択ができるよう支援する。
(5)教育環境の整備
- 清掃指導の徹底により 、清潔な環境づくりに積極的に努める態度を育成する。
- 各教室 、廊下 、特別教室 、校庭等の掲示・植物等の配置を工夫し 、うるおいがあり美 しい環境づくりに努める。
- 掲示や放送等の工夫により 、学習意欲が高まる環境づくりに努める。
(6)研修の充実
- 指導力の向上を図るため 、全員が年1回以上授業研究をおこなう。
- 校務分掌の中に教育情報担当を中心に 、教育情報の収集・整理・提供に努め 、職員の資質向上のための条件整備を推進する。
- 指導と評価の一体化を図るための指導方法の研修に努める。
- 昨年度の研修の成果を伸ばすとともに 、「授業錬磨の公開日」等を活用し学習指導方法の向上を図る。
- 新学習指導要領の移行期に伴い、全面実施に向け改訂の内容の理解を図るための研修に努める。
(7)特別支援教育の充実
- 特別支援教育コーディネーターを中心とした校内委員会を充実させる。
- 「個別の指導計画」 「個別の教育支援計画」を活用し 、生徒個々の教育的ニーズに応じた継続的な指導や支援を行う。
- 保護者やスクールカウンセラー 、関係機関等と連携し 、支援の充実と就学相談を行う。
(8)家庭 、地域社会との連携の強化
- 家庭・地域教育力の向上と地域の力を生かした活動の推進を図る。
- 学校公開や学校評価の実施等により 、地域社会に根ざした学校改善を推進する。
- 関係諸機関・団体等との連携により 、生徒の安全確保及び健全育成を図る。
- 保護者会・学校公開・各種便り・情報メール等を活用し 、学校の情報を伝達する。
(9)業務改善の推進
- 業務適正化の観点から、学校や教員の業務の見直しを図る。
- 「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」に基づき、部活動の適正化の推進を図る。
- 長時間労働という働き方について、教職員一人一人の意識改革を進める。
|
|
|